第1回金融専門人材に関する研究会議事要旨
1.日時:
平成19年11月19日(月)15時00分~16時30分
2.場所:
中央合同庁舎4号館9階 金融庁特別会議室
3.議題:
○メンバーの紹介
○オブザーバー(事務局)説明
○自由討議
○事務連絡
4.議事内容:
○渡辺金融担当大臣より挨拶があった。
○事務局よりメンバーの紹介があった。
○事務局より今後の検討課題について説明があった。
○自由討議における主な意見は次のとおり。
(期待される役割について)
当局と市場とで共通のコンプライアンス知識を持ったリーダーを育成する必要がある。
法律と現場をつなぐ役割を期待したい。
法律について、弁護士ほど知識が深くはないものの、一般社員よりは深いレベルで知っていて、全体を見渡して経営者に助言できるような人材を育てていくのが望ましい。
資格がパスポートとして機能し、人材の流動化が進むことが最も重要。
金融分野に進む法学部生や経済学部生のモチベーションとなるようなキャリアパスが描けるか。
金融商品取引法などの授業の知識が根付くためのキャリアパスが必要。
専門職大学院修了者や司法試験・公認会計士試験合格者にとっても選択肢となる社会的に高度な資格として認知されるような資格とする必要。
権限や処遇(社内でのステイタスやライン)の明確化が必要。
(求められる資質について)
金融関連法制についての知識、コンプライアンス意識。
法律学と経済学の思考体系のバランスが重要。
どの業種にも必要なベーシックな知識がある。専門知識が必要な分野に一定の能力検定を設けては。
専門分野に止まらず幅広い目配せができる人材が必要。
現場感覚が重要。
日本の金融市場の国際化の観点から、英語は不可欠。
ある程度の法律知識は絶対に必要だが、インハウスロイヤーとの違いを明確化する必要。
法曹資格に加えて特別の資格を取った人がインハウスロイヤーとなることも考えられる。
(その他の論点について)
仕事を辞めないと受からない資格とするべきではない。
試験一本にするよりも、学ぶプロセスを重視すべき。
資格だけでなく人的ネットワークが重要。
受験資格、実務経験やインターンシップとの関係を今後議論すべき。
法科大学院、会計大学院、MBAとの連携も考慮すべき。
実務経験の積み重ねが重要。
日本の金融工学には実務の経験則が織り込まれていない。
継続教育によって新法や法改正に対応していく必要がある。
(以上)
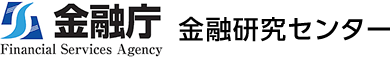
 検索
検索